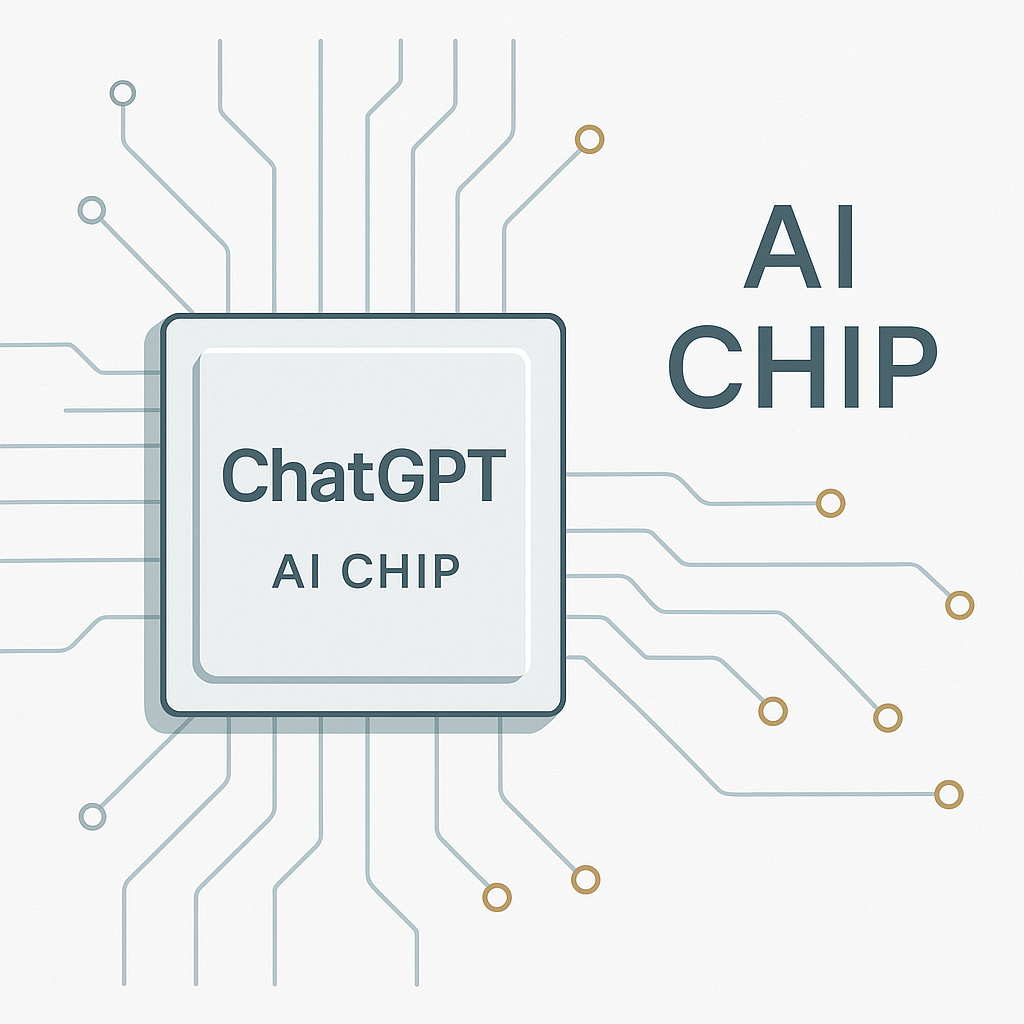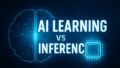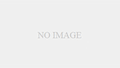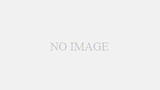半導体覇権の行方|日本の失速と世界の台頭、その本当の理由とは?
かつて「半導体王国」と呼ばれた日本。
1980年代には、世界の半導体売上ランキングの上位を日本企業が占め、シェアは世界全体の50%以上に達していました。
しかし、それから40年近くが経ち──
現在ではその面影も薄れ、日本の存在感は大きく後退しています。
その一方で、台湾・韓国・アメリカなどの企業は着実に技術力と市場シェアを伸ばし、
“半導体覇権”の中心を担う存在へと変貌しました。
なぜ日本は、ここまで遅れを取ってしまったのか?
どこで何を見誤り、他国は何を学んだのか?
そして、日本の新たな挑戦は過去の失敗から何を活かそうとしているのか?
この記事では、日本半導体産業の「栄光と失速」、
そこから世界が学んだ戦略、そして日本が再び立ち上がるために必要な視点を、やさしく丁寧に解説します。
1. 日本の黄金時代:かつて世界を制した半導体産業
1980年代、日本の半導体産業は“世界最強”の名をほしいままにしていました。
NEC、東芝、日立、富士通、三菱電機──
これらの企業が世界の売上ランキング上位を独占し、1988年には日本が全体の約50%のシェアを獲得していました。
その成功を支えたのが、次の4つの要素です:
- 高い製造技術と品質管理:垂直統合型モデルによる安定供給
- 政府の支援:VLSIプロジェクトなど産官学連携の技術開発
- ものづくり文化:現場力と改善活動の積み重ね
- グローバル展開力:輸出主導のビジネスモデル
このような成功要因が、絶妙なバランスでかみ合っていたのが1980年代の日本でした。
2. 失速の理由:3つの転換点と構造的課題
日本の失速には、単一の原因ではなく、複数の「転換点」が重なったことが背景にあります。
① アメリカとの貿易摩擦と外圧
日本製半導体の台頭に危機感を抱いたアメリカは、1986年に日米半導体協定を締結。
この協定により、日本企業は価格の監視やアメリカ製品の受け入れ拡大を強いられ、
事実上、自由な競争環境から排除される形となりました。
技術で勝って、ルールで敗れる──この体験は、日本にとって大きな教訓となりました。
② 分業化の波への対応の遅れ
1990年代、世界の潮流は「垂直統合」から「水平分業」へと変化。
- ファブレス(設計専業)企業:Qualcomm、NVIDIAなど
- ファウンドリ(製造専業)企業:TSMCなど
しかし、日本は依然として自前主義に固執し、
スピードやコスト競争力で世界から遅れをとるようになります。
③ 政策の“手放し”と産業の空洞化
1990年代後半以降、日本政府は「民間主導」を掲げ、半導体政策を縮小。
一方で、半導体は社会インフラとも言える基幹産業。
長期的視点と国家的支援がなければ、立ちゆかない分野でもあります。
この“手放し”が、技術継承や人材育成の空白を生みました。
3. 世界の動き:台湾・韓国・アメリカは何を学んだか?
台湾:TSMCという“影の主役”
1987年に誕生したTSMC(台積電)は、設計を行わない「製造専業=ファウンドリ」モデルに特化。
AppleやQualcommなど、設計に強みを持つ企業の“製造パートナー”となることで、
世界の製造インフラとして確固たる地位を築きました。
韓国:一点集中と国家支援
韓国は、サムスン電子を中心に、DRAMやフラッシュメモリに特化。
政府の巨額支援と企業の集中投資が重なり、世界トップレベルのシェアを獲得。
「政府が守るから企業は攻めろ」──韓国流の成長モデルが機能した背景です。
アメリカ:スタートアップ生態系と分業
アメリカでは、半導体スタートアップが設計分野で急成長。
- NVIDIA:GPU設計に特化
- Broadcom/Qualcomm:通信やスマホ向けSoCを設計
大学・研究機関・ベンチャーキャピタルとの連携が、
革新的な設計力とスピード感を支える基盤となっています。
4. 日本が再び挑むために必要な3つの視点
① 「すべて自前で」は限界
現在のグローバル市場では、特化と連携の戦略が主流です。
ラピダスがカナダのテンストレントと提携したように、
日本も「すべて自前」から脱却し、強みを活かし、外部とつながる姿勢が求められます。
② 国が当事者となる覚悟
CHIPS法を通じて国家が直接動くアメリカ、
TSMCに積極投資する台湾政府──世界では「国家がプレイヤー」として動いています。
日本でも、ラピダスへの1兆円支援に象徴されるように、
国が能動的に産業を育てる時代に入っています。
③ 長期的投資と社会理解の醸成
半導体産業は“短期成果”を求めにくい領域。
「10年後の未来を創る」という視点での、継続的な支援と
社会全体の理解・共感が不可欠です。
5. まとめと読者への問い
1980年代、日本は世界最強の半導体大国でした。
しかし、転換点を見誤り、時代の変化に対応できなかった結果、
現在の後退へとつながっています。
ただし、それは“過去の話”で終わる必要はありません。
いまラピダスや政府が見せているように、
「もう一度、立ち上がる準備」は整いつつあります。
あなたは、半導体の未来に何を期待しますか?
10年後の日本が、再び技術で世界に貢献できる日が来るとしたら、
それは、あなたの関心と理解から始まるのかもしれません。
🔍 用語解説
- ファブレス:工場を持たず設計のみに特化した企業。例:NVIDIA、Qualcomm
- ファウンドリ:他社設計の半導体を製造する企業。例:TSMC
- CHIPS法:米国が半導体産業強化のために制定した補助金法案
- ラピダス:日本主導の次世代半導体製造プロジェクト企業
- テンストレント:カナダ発のAI向けプロセッサ企業。ジム・ケラー氏がCEO
🔍 参考リンク・資料一覧 ※リンクは、削除変更される可能性があります。
経済産業省|半導体・デジタル産業戦略(2021年6月)
経済産業省|次世代半導体技術の研究開発拠点整備事業について(LSTC)
内閣官房|経済安全保障の推進(国家戦略)
日本経済新聞|なぜ日本の半導体は敗れたのか(特集記事)
日経クロステック|ラピダスの挑戦と日本の再起(2023年特集)
SEMI Japan(半導体産業団体)|世界の半導体製造分業の現状
Bloomberg|TSMC、サムスン、米国CHIPS法の概要と支援戦略(英文)
Tenstorrent 公式プレスリリース|ラピダスとの提携発表(2023年11月)